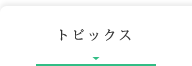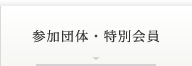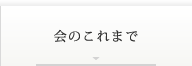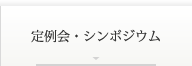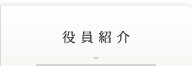第35回「健康と経営を考える会」定例会開催レポート
健康と経営を考える会事務局
「健康と経営を考える会」第35回定例会(会員のみ参加)を、会場(同友会ビル会議室 文京区)× オンラインで3月19日(水)に開催いたしました。
今回は、「外食産業の保健事業 ~生活習慣の現状と禁煙・BMIの取組み~」について、すかいらーくグループ健康保険組合・匂坂常務理事、「ロコモについて知ろう ~現役時代から始めるロコモ対策」について埼玉県立大学・山田准教授、「これからの健康経営」について経済産業省・山崎ヘルスケア産業課 課長補佐からご講演いただきました。

すかいらーくグループ健康保険組合・匂坂常務理事 講演
外食産業の保健事業 ~生活習慣の現状と禁煙・BMIの取組み~

すかいらーくグループの被保険者は、約2万人で、このうち5千人が正社員、残りは全部パート・アルバイトという構造です。そのパート・アルバイトの方は、毎年3割から4割は入れ替わっているという特殊な人員構成となっています。
常務理事に就任して5年間で行ったことが、健康経営の部分をさらに深掘りすることと、「体制図」・「戦略マップ」作りです。これらは全て自分で作り、グループ本体の会長と社長に直談判、承認をもらってホームページに掲載しています。
外食産業は不健康な従業員が非常に多く、朝ごはんは食べない、シフト制のため就寝時間はバラバラという状況でした。
こうした問題に対応するために行ったことが、経営トップからタイムカード打刻を正しく行うことでした。そうすることで正しい労働時間を記録された従業員の健康診断結果を見て、課題を正確に把握できるようになりました。
すかいらーくグループでは、重症度の高い対象となったら、本人だけではなく、上長にも報告し、この従業員の健康管理は上長の仕事でもあるということを告知する仕組みにしている。
私が人事部長をしているときに、健康診断を受けない人に対しては、本人だけでなく、上長も連帯責任で5%カットとしたところ、健診受診率は急に上がった。
健康診断、労働時間の労務管理が正確に出るようになり、実態がわかったので、社内ルールとして、上司の仕事の職務基準の中に、部下の健康管理を入れました。そうすることで、本部では改善が見られたが、工場とお店は少し悪化している。これは、パート・アルバイトが年中入れ替わることで、下がりにくい状況である。
スコアリングレポートを活用し、生活習慣の現状と取り組みについて、取組みの優先順位を決めて行っており、一番やらなければいけないことは禁煙、食事である。
禁煙については、その重要性を、前任の酒匂さんが経営陣にすり込んでくれたので、経営陣がまず、禁煙に関してはやる気を持っている。そのために、今、以下5つの施策を柱として動いている。
①禁煙重点階層の設定をして階層別に攻める、②規定ルールを決めて縮々と実行、③インセンティブ設定、④禁煙サポート事業展開、⑤採用基準や登用基準見直し
それら施策により喫煙率は、右肩下がりで減っている。
①禁煙重点階層とは、会社の中で階層上位・役員層から順に禁煙について攻めていきました。
役員層は、喫煙者がほぼいない状況です。今は、全国3000店の店長対象に取組みを進めているところです。会社の健康労務チームのリーダーが、元健康保険組合の職員で、毎月の棚卸しの時に、食材のみでなく、従業員はタバコを捨てるか捨てないかの棚卸しデータも入れないと月利送信が送信できない仕組みにしました。毎月、全社の喫煙者棚卸しができる形になったので、これを今度インセンティブにかけ、競争できる形にしました。
②規定・ルールは、会社の建屋内禁煙から、従業員もお客様も敷地内禁煙、同時に就業規則変更した。
③インセンティブ・表彰については、禁煙成功者とサポート者対象に食事券配布している。また、タバコを吸う人も吸わない人も、1年間タバコを吸っていない履歴があればポイントがつく制度も、今年度の秋以降に始める。
④禁煙サポート事業としては、禁煙ガム、禁煙アプリ、Eラーニングも行っているが、最も効果があったのは社長のお手紙です。社長のお手紙で、健康診断の結果、タバコを吸っていると答えた人に社長名でお正月に年賀状が届くようにしました。その年賀状では、「すかいらーくは禁煙をずっと推進していること、お客様には綺麗な空気の環境で食事を召し上がっていただくよう努力していること、これらを継続するためには従業員も綺麗な空気の環境で生活するのが当たり前になるような人たちでいたい、本人一人ではやめられないかもしれないけど家族のご協力があればやめられるかもしれないのでぜひお願いします」というお手紙です。
⑤採用・登用のところでは、2020年より中途入社の非喫煙者しか取らない、2021年からは新卒も非喫煙でなければ正社員で採用しない、採用の内定承諾書類に、タバコを吸う場合は入社までにやめることを宣言することを記載し会社に提出するということにしている。2023年からは、タバコを吸う人がどんなに成績が良くても上位職に登用しないことをルールとしました。
BMIは、事業所別で見ると、メンテナンス清掃をやっているところが一番悪い。メンテナンス清掃は、店の営業時間の関係で、夜中の3時から明け方の6時ぐらいまでの間に掃除を一懸命している部隊だから昼夜完全に逆転しているような人がいる。その部隊の人たちは、健康的にはよくない。どうしても余計に4食ぐらい食べてしまう影響もあるかと思われる。
基本的にすかいらーくグループ従業員は、まかない食で食べるため、揚げ物屋に配属になった人は揚げ物しか食べず太りやすくなるため、BMIが高くなる。営業本部長たちに対して、自分たちの部下が病気で倒れないようにするためにメニュー提案、野菜がもう少し摂取できるようなメニューを増やし、お客様に販売すると同時に従業員も食べられるようにすることを提案している。
埼玉県立大学 保健医療福祉学部/大学院研究科 山田准教授 講演
ロコモについて知ろう ~現役時代から始めるロコモ対策

人間というのは、突き詰めれば動物なので、結局は歩く・移動するということを保つことが、重要だと思っています。15年ほど前のJAMAという有名な雑誌に載った論文では、大股でスタスタ歩く、見た目も元気な人は、寿命も長いということがわかっていて、人間が動物であり、動くことは全ての基本であることを示しています。
ロコモティブシンドロームとは何か。運動器の障害のために、移動機能の低下をきたした状態で、進行すると、要介護のリスクが高くなる状態と言われています。つまり、移動機能低下=ロコモティブシンドローム(ロコモ)ということで、国内の40代以上で、4660万人がロコモだと推計されており、高血圧や糖尿病の有病者数を上回り、また、健康日本21・第3次ではロコモ(足腰に痛みのある高齢者)の減少と、骨粗鬆症検診受診率向上が国の目標に設定されています。
このロコモは、日本整形外科学会が2007年に提唱したものです。
整形外科の現場では、高齢者が骨折を繰り返すのは骨が脆くなる病気があり、高齢者の運動を生活ベースでなんとかできないか、という思いがありました。
そこへ、国の方針として2007年4月、新健康フロンティア戦略で、介護予防対策の一層の推進(介護予防力)が重点分野となり、この中に骨関節、脊椎の痛みによる身体活動低下、閉じこもりの防止という項目があり、運動器障害のために要介護になる危険性の高い状態を啓蒙するためにロコモティブシンドロームということで出てきた概念です。
運動器とは、自動車のエンジンやタイヤのようなもの、もしくはボディで、1個タイヤが潰れてしまったら動けないわけで、非常に重要です。日本の高齢化は世界第一位のスピードで、戦後の平均寿命が男性50歳、女性53.9歳であったのが、現在ではもう80から90になっていて、結果として運動器疾患を抱える人は急増しています。2000年に介護保険が始まって以来、当初6兆円だったのが要介護給付費は約3倍となっており、金銭的にもいろいろな負担が出てきています。
加えて高齢者の最も多い体のトラブルは足腰の痛みです。男女ともに1位が腰痛、それから手足の関節が痛むというのは、必ず3位までに入ります。整形外科の入院患者は50歳以上から急増します。
整形外科の患者数は二峰性です。10代の元気な若者、スポーツ障害の方々で、少し多くなり、50代を増えると、一気に入院患者が増えます。人生50年という言葉がありますが、整形外科的に言っても、運動器の寿命もおそらく50年くらいで、その後は丁寧にメンテナンスしながら使っていく、もし必要があったら人工股関節を入れることが必要だと思っています。
健康寿命と平均寿命には差があり、自分で歩けることは、生活の質のためにとても重要です。健康寿命を短くする原因としては、メタボ、フレイル、ロコモの3つが、介護予防や健康寿命のためには重要です。
フレイル・ロコモ共同宣言というのが、学会80団体一緒になって2022年の4月に出され、加齢に伴う人の体の問題についてまとめています。生活習慣病、メタボ、プラス痩せ(特に女性)があり、高齢となる最終像としてフレイルがある。それを繋ぐ概念として、ロコモがあるという位置づけになります。40・50代、勤労者のロコモ・メタボは、膝の問題もあり、血圧を下げるために歩いてくださいと言っても歩けない。ロコモとフレイルが特に男性で、肥満と絡んで悪くなることが最近の研究結果でも出ています。
健康日本21(第2次)では2013年にロコモの認知度を80%まで上げることで取り上げられました。20%から45%ぐらいまで上がるのはスムーズで、それ以降上がらず、ロコモは介護ということで、高齢女性には結構響きますが、若い人には響きませんでした。
ロコモの評価法は以下3つとなります。①2スップテスト:地面に対して水平の力、歩く能力を見るテスト、②立ち上がりテスト:10cm、20cm、30cm、40cmの台から片足もしくは両足で立ち上がり体重を支える力があるかどうかを見るテスト、③ロコモ25:身体の状態、生活状況に関する25の質問です。
このロコモ度テストの臨床判断値が2015年に出てきました。この3つのテストで、どれか1つでもダメならロコモと判断します。ロコモ度0は何もない状態、ロコモ度1が移動機能の低下が始まっている状態、2が進行している状態、3は移動機能の低下が進行して社会参加に支障をきたしている状態で、これがフレイルとなります。
ロコモ度テストの基準値を作るという目的で、ロコモ対面1万人調査を2017年から2019年まで行いました。これは全国の大学や医療機関の協力を得て行った調査で、128681人のデータをまとめ、ロコモの該当率、年代別基準値、ロコモ度と年齢、生活習慣などの関係を調べています。2ステップ値は少しずつ若い頃から下がり、立ち上がりテストは60・70代から一気に下がおります。ロコモ25は70代から一気に上がるが、弱年層でも少しずつ悪化、20代でも1歳上がるにつれてロコモ度1のリスクは上がります。
調査により、月数回の運動でもロコモの予防効果の可能性がある、生活習慣、メタボのある人はロコモになりやすいし逆も然りということが分かってきた。この1万人調査のデータによりロコモ年齢というアプリを作っています。これは自分の状態を知ることで気づいてもらう、3ヶ月に1回測ることで良くなったか悪くなったか見てもらうというアプリです。
2024年に健康日本21の第3次が始まったところで、ライフコース全般にわたって動くこと歩けるというロコモの重要性が認識されているところです。ロコモティブシンドローム対策が、この健康日本21の数値目標として入っていることを受けて保険者の加算減算指標にも入っているのだと思います。
歩行速度は、平均で見ると、加齢とともに徐々に低下し、70代くらいから一気に低下します。個人の低下に注目すると、「80代ぐらいまで落ちずに一気に落ちる人」、「40代ぐらいから低下している人」など、すごく差があります。個人の少し悪くなり始めたところ、ロコモになりかけている人を検査で捕まえて対策を講じるためにロコモインターネット1万人調査を昨年度、日本整形外科学会により行っています。25の質問の中で、「痛み」に関しては若いうちから結構持っている方が多い。足の痛みは加齢とともに上がっていきます。背中や腰の痛みは30代から上がり、なだらかに増えていきます。年齢が上がると増えるものとしては「階段の上り降り」「急ぎ足で歩くのがつらい」「休まず歩ける距離が短くなる」「スポーツや踊りが困難である」ことに関して悪くなります。最初にこうした症状が出ることが分かり、ロコモになる前の最初の兆候が明らかになったということで、この4つのうち一つでも出てきたらロコモについて考えてください、対策をしてくださいという「ロコモサイン」というものを日本整形外科学会より発表しました。
運動生活運動習慣がなさすぎ・しすぎ、運動器の病気、痛みや機能障害放置、痩せすぎ・肥満がロコモの原因となります。ロコモ対策としてどんな運動がいいかということは、NEAT(非運動性活動熱産生)、つまり日常の生活活動で消費されるエネルギー、立ったり座ったりとか、こまめに動くというところで、隙間時間でちょっと強い運動、小走りや階段などを行うと平均年齢61.8歳で6.9年調べたところ、1日4.4分の少し強度の強いこうした運動を行うと死亡リスクや心血管障害死亡リスクが下がることが分かっています。少し歩くことと、立ち上がることでは、使う筋肉が違います。歩くのは慣性の法則で歩けてしまうが、立ち上がるのはしっかりした筋力が必要です。立ち上がるという運動を少し日常生活に入れることがポイントだと思っていますロコモチャレンジ推進協議会では2つの運動を推奨しています。一つは片脚立ちで、60秒間片脚を少し上げて立っていただく。バランスを鍛える運動を行うと股関節の骨密度も上がりますし股関節症対策にもなります。もう一つはスクワットです。我々がお薦めしているのは膝がつま先の前に出ないスクワットです。後ろに椅子があると思って肩幅より少し足を広めに立ち、つま先30度ぐらい外に開いてください。注意点は膝がつま先の前に出ないようにしてください。ゆっくり降りてゆっくり上がる、5回で1セットを1日3セット、最低2ヶ月やっていただくとよいです。心配な方は椅子を後ろに置いていただくと転んだ時にも安心です。ベンザスクワットという別名で、トイレに座る時のイメージになります。くれぐれも膝の軟骨が痛まないよう膝がつま先の前を出ないように気をつけてください。
運動機能は20代がピークでどんどん下がっていきますが、40代ぐらいから自分の体が何に起こっているのか、自分がどういう状態なのかを知ることが大切です。ロコモ度1のうちにロコモ対策する。同年代の他の人よりも少し歩く速度が遅くなってきた、もしくは40センチの椅子から立ち上がれない場合には対策を行う。痛みがある、ぎっくり腰、足に痛みがある場合には治療する。将来より重症になることを防ぐことが非常に重要だと思っています。
経済産業省商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 山崎課長補佐 講演
これからの健康経営

もともと経済産業省が健康経営に取り組み始めた背景として、少子高齢化があり、生産年齢が2050年までに30%減少する中で、これから人口オーナス期の企業のあり方、人を大事にしていかなければいけないというところを健康経営を進めることで取り組んでいただきたいという経緯がありました。生産年齢人口が減っていく分を、皆さんが元気で健康に長く働き、健康寿命を74歳まで延伸できたとすれば、生産年齢人口の割合が66%、2007年時点と同様の水準まで回復し得ることも考えられます。
経済産業省のヘルスケア政策としては、「健康経営の推進」を第一に10年以上取り組んでいます。その他に時代に応じて「パーソナルヘルスレコード」という、個人の健康情報をデジタルで活用していくことによりカスタマイズされたサービスを作る、「質の高いヘルスケアサービスを創出」するために、エビデンスベースで医学会指針等と連携しながら進めることを行っています。また、介護や認知症の地域課題の対応ということで、昨年の3月にも、「仕事と介護の両立を支援するためのガイドライン」を経営者向けに出しています。「ベンチャー」や「国際展開」も支援しているところです。
最新の認定状況については、今年は大規法人が13%増、3400件の認定がありました。中小企業は申請数で今年初めて2万社を超え、認定は19796件という状況です。中小企業部門については、今年度からブライト500の下に、ネクストブライト1000という冠を新しく設けました。
健康経営銘柄2025
今年度は29業種53社を選定しています。上場企業に占める業種別の健康経営度調査票・回答比率を調べたところ、「電気ガス業」が高い状況です。伸び率としては「倉庫・運輸業」が増加し、もともと取り組みが少ない業種でしたが、業界の皆さんの意識が高く、経産省も国交省と連携してトラック業界や、業界団体の皆さんと健康経営セミナーを行うことも始めています。今後はそうした業界ごとの取り組みも進めたいと思っており、皆様の業界団体で健康経営セミナーをやりたいという声がありましたら、経産省や事務局に連絡いただければと思います。
大規模法人部門
大規模法人で都道府県別に健康経営取り組みを分析すると、滋賀、奈良、島根、高知、大分県で取り組み率が高い。他方、青森、栃木、山口、愛媛、宮崎県では、あまり取り組まれていない地域特性があります。この分析の趣旨は、自治体や各地域の商工会議所、協会けんぽに見ていただき、地域の取り組みを進めていただきたいということで出しています。調査の継続回答率は8割ほどで安定、離脱率は1割未満となっています。フィードバックシートの開示状況は、開示比率は全体で約7割、昨年度よりも213社増加、2679社が開示しています。
中小企業法人部門
都道府県別のカバー率(認定法人数/中小企業数)が高いのは、岡山、愛知、鳥取、山形県です。都道府県別の認定が前年度比で高かったのは、青森県、富山県、長崎県でした。認定数が伸びた県の中には昨年度、健康経営セミナーを開催したところもあり、今年も事務局と連携して、夏に各地域でセミナーを開催したいと考えています。中小企業の不認定理由は、約9割の法人が健康宣言の実施ができていなかったことで、具体的な推進計画ができていないところもあります。継続回答比率は、中小企業の場合でも8割弱が継続されている状態です。中小企業の場合にはどうしても少ない人数の中で担当できる人がやめると途切れてしまう事例が、大規模法人と比べると多い状況です。フードバックシートの開示状況については、ブライト500申請法人のうち84%が開示しています。
健康経営の可視化と質の向上
健康経営施策の今後の展開については、引き続き、個人、組織、地域社会あるいは国際社会にも影響を与えられるような健康経営でありたいということで、効果の可視化と質の向上を進めていくと同時に、新しい健康経営を支援するサービスを拡大し、2024年度1年間をかけて『改訂版 健康経営ガドブック』を作成していただいています。このガイドブックで、新しく出てきているポイントとしては、健康風土が会社の中に蓄積されていくことが、健康経営の一つの意義であることを示しています。もう一つが、社会関係資本、従業員間や組織内の相互の信頼やネットワーク、心理的安全性が高い関係性と、これらが健康経営を実践していく中で構築されるというところを明記しています。このガイドブックでは、この他にも健康経営で構築されることや、KPIとしてどのようななものを使ったらいいかということも詰め込まれているものになります。ACTION!健康経営で公開されていますので、ぜひご覧ください。
健経経営を進めるとき、従業員一人一人が健やかでエンゲージメント高く働ける環境を整えることが、健康経営の価値になっていきます。これを進めるときに経営層が関与することが一番早いということで、経営レベルの会議でも効果検証をぜひやっていただきたいということが、今年度調査表の中で経営層の関与を問う経営レベルの会議で取り上げた頻度について評価をしました。2025年度は回数だけではなく、多面的に経営層の関与のやり方、年度ごとに経営者がメッセージを社内外に発信するなど様々な方法について検討しています。
PHR活用もぜひ進めていただきたいと思っており、新しい設問を設けて状況を聞きたいと考えています。大規模法人の多くはPHRを活用しており、健診情報だけでなく、ライフログデータも使っているところはあります。データを活用できているところは半分ほどという状況でした。2025年度以降は、従業員自身がPHRを活用できる環境整備状況の深掘りをしていきます。より従業員自身が主体的に健康づくりをできるような環境をサポートするところを評価項目とし追加するよう考えています。
健康経営を行うときに、支援サービスをうまく使うことも大事ですが、支援サービスがどこにあるのかわからない、事業者がどんなことをしているのか調べることが大変だという話もあり、領域別にサービス事業者のリストアップをしていくことを進めています。ACTION!健康経営では、PHRサービスのリンクが貼られていますので、参考にしていただければと思います。
2025年度には、女性の健康の効果検証プロジェトを進めていきたいと思っています。これは2024年に女性の健康課題に取り組まないことによる社会経済損失、年間3.4兆円を試算しました。女性の健康に関するポジティブインパクトについては、データが少なく、企業の中で女性の健康に取り組むことについて経営者から理解されづらいという声もいただいているので、企業の皆さんにご協力いただき、半年間女性の健康に取り組んでいただき、その前後で社員アンケートを取ってもらい、プレゼンティーイムズの改善や、この会社で支援が感じられるようになった、この会社で長く働き続けたいと思うようになったなど、アンケートを取っていきたいと思っています。
この女性の健康の効果検証は3ステップあります。「ステップ1」何もしていないのでまず施策を始めたいところ、「ステップ2」やってみたけど使われておらず利用率アップを重点的に考えたいところ、「ステップ3」やれることは全部やっているが効果検証までいけていないところです。プレゼンティーイズムやアブセンティーイズムなど効果検証のあり方について取り組んでいくということで、具体的には事前・事後のアンケートとステップごとの座談会により、意見交換、各社のナレッジをシェアすることを進めていきたいと考えています。女性の健康課題はデリケートで制度利用へのためらいがあることに配慮し、まず経営層からのメッセージ発信や管理職研修を行い、理解を促進するところから始め、組織体制を組んだ上で具体的なリソースを付与支援、PHRを活用等の投資を行うことがよいのではないかと考えている。女性の健康課題に対する取り組み事例集も公開しました。この中では大企業と中小企業とそれぞれに事例紹介するとともに明日から真似できる取り組みも紹介しています。例えば生理用品をトイレに設置、無料のオンラインセミナーや地域の市民講座を従業員に案内するといったすぐできるものを活用する方法もあると思います。
心の健康実践ガイドも出します。メンタルに対する取り組みは各企業悩まれているところだと思いますので、取り組み方や取り組みの意義をまとめて実践ガイドという形で出します。
新たなマーケットの創出
ウェルココという、メンタルサービスに関して企業の課題別にサービス提供事業者のリストを、2025年秋に公表予定でいます。この領域は、デリケートなため、一定の有効性が確認されたサービスだけをリストアップすることにして川上先生含めた先生方に監修していただきながらリストを作っているところです。中小企業向けのメンタルヘルスサービスを活用できる実証事業も行う予定で、こちらは補助事業という形で行います。その他にも成果に応じた支払い方式の導入PFS(Pay for Success)という仕組みを健康経営の中でも普及を進めており、肥後銀行がこうした取り組みをおこなっています。
国際展開も行っており、2024年秋にISO25554という健康経営のエッンスを盛り込んだウェルビーイングを高めるための取り組みをISO化したもので、何をウェルビーイングとするかについても組織が決めるものですが、組織が自分たちで決めるというところからガイドしているものです。ISO25554のフレームワークをベースとして健康経営を国際的にも使っていただけるよう指針を作ることを目指しています。また欧州を中心としてOECDと連携をして健康経営が国際的に通用するようKPIを策定することも進めていきたいと考えています。世界的に健康経営が広がっている一つの事例として、フィジーで健康経営が取り組まれています。これはJICAの事業として日本の方がフィジーで健康経営度調査をベースにしたチェックリストを作り企業にPRしている状況です。
健康経営の社会への浸透・定着
2025年度に進めていくこととして、多様な働き方への対応はやっていきたいと思っており、非正規の方への健康経営の取り組みはぜひ進めていただきたいと思っています。大規模法人の89%で他社からの派遣社員を抱えている状況で、健康経営を派遣社員にも取り組みを進めている企業の特徴については、「派遣元企業と派遣先企業で従業員の状況をシェアしているところが健康経営の取り組みが進んでいる」という関係性がみられたので、こうした情報交換を派遣元と派遣先で行うことから始めていただいてはと考えています。
若年層にも浸透を進めていきたいと考えております。大阪府では、就活生のパンフレットとして健康経営の漫画を作っています。富山では富山大学の学生さんたちに協会けんぽが中心となり健康経営に取り組むホワイト企業についてリストをパンフレットとして渡す事例もあります。パンフレット配布後には、富山県内企業から健康経営の進め方について質問も出ていると聞いています。他にも大学では講義が様々なところで行われており、若い人たちに早いうちから健康経営を知っていただき、企業選択にもつなげていただければと思いますし、自分自身のリテラシーを高めていただくことも大事だと思っています。
運輸業界への普及ということで、運輸業界とは今年度いろんな取り組みを業界団体や新しいサービスも出てきていて、東京海上ホールディングスが事務局の物流コンソーシアムbatonが業界で連携して健康経営を取り組む動きもあったり、マイメディカというヤマト運輸が健康経営の取り組みとしてオンライン診療につなげる健康管理と重症化予防を行うサービス、システムを自社で作ったのですが、そのシステムを利用料無料で他社にも使える形でサービスを公開しています。こうした自分たちの健康経営を新しい事業につなげる事例が徐々に出ていると思っています。是非、そうした動きが広がっていくと経済産業省としても産業としての厚みが増していくということで、ご紹介させていただきました。
健康経営・データヘルスに熱心に取り組む会員団体の方73名にご参加いただき、盛況のうちに閉会となりました。